



寒暖差が激しく、体調を崩しやすい時期となりましたが、子ども達は支援に楽しく参加しております。今回は、支援内容を一つ紹介させていただきます。皆様は、ごっこ遊びと言ったら、子ども達がお友だちや1人で楽しく遊んでいるイメージを持つ方が多いのではないでしょうか?支援内容に、ごっこ遊びを入れているお子さんもいます。遊びの中で、幼児は社会的遊びを通して他者との相互交渉のやり方や他者理解を発展させています。例えば、ごっこ遊びでは他者と自身の遊びのイメージにズレが 生じる場合があるます。このずれを通して他者は自身と異なる信念を持っていることや、他者の言動の背景には意図があることに気付き、他者から了解を得たり、イメージを明確にするための会話を発展させていくことに繋がります。
他にも、ふり遊びや見立て遊び、ごっこ遊びは象徴遊びと呼ばれるもので、こどもの発達にとって重要な役割を持ちます。
想像力や社会性、言葉の発達に関係してきます。
指導員が遊んでいる様子をみて、相手がどう思っているか、やり取りを見てもらい自己コントロールに繋がる意味もあります。
遊び一つでも、さまざまな視点、観点があり今後も、強みを活かし、弱みを伸ばす支援を心がけていきます。どうぞ、よろしくお願いします。
ねらい
①何時にどんな生活をしているか、理解する
②時間を意識して生活する
③自分の生活リズムを振り返り、改善しようとする



写真①②について
帰宅してからの生活を振り返ってもらいました。
目で見てわかるように、行動をイラストにして、並べてもらいました。
これを見ると、みんなの生活の行動の順番がすこしずつ違っていること、そして、一人一人、それぞれの毎日のルーティンがあることがわかりました。
特に、寝る時間は午後8時から10時まで、いろいろだったので、睡眠がいかに大切かを一緒に考えました。寝る時間が遅くなっていることがわかると、もう少し早目に寝るようにルーティンを見直してみようということになりました。
この機会にお子様の毎日のルーティンについて、一緒に話し合ってみられてはいかがでしょう。
写真③はひまわり教室到着時のお支度の順番をわかりやすく、一覧にしたものです。
ねらい
①目で見てねらいを定める
②距離感、ボールの種類などの確認
③調整して、適切に必要な体の部位を動かす

みんな、ボールやお手玉投げは大好き!集中して取り組むことができました。
写真④は、お手玉ビンゴで、3×3の輪の中にお手玉を投げ入れ、横か縦か斜めに並べるゲームです。入れたい場所に、ねらいをつけて投げる瞬間、頭、手、足の位置を上手に調整できていますね。ねらった場所に入ると嬉しそうでした。見ているお友達も、応援して、一緒に楽しみました。
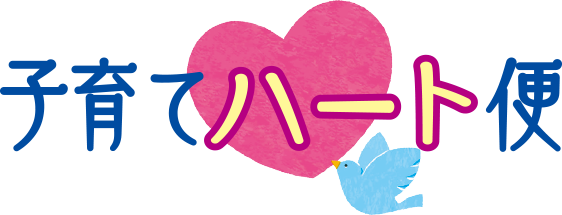

3月からひまわり教室の児童発達支援に勤務しております長尾美奈子と申します。その前は川崎市の児童発達支援事業所で指導員をしておりました。危険生物や昆虫、海洋生物などが大好きなので、趣味が合うお子さんや保護者の方たちとお話ができたらいいなあと思っております。また、今は社会福祉についても学んでおります。現在はお子様の支援をしておりますが、いつかお子様から高齢者までのさまざまな支援に取り組めたらいいなあと、夢かもしれませんが考えております。
毎日が勉強中の身ですが、一生懸命に取り組んでまいりますのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C) 社会福祉法人杉の子会 All Rights Reserved.